今週もテニス教室に行ってきました。
お目当ては、95歳のAさんです。
今回は、どんな奇跡を見せてくれるのでしょうか!

ボールに反応しない
あっ、いました、いました。
「おはようございま~す。」なんて、まだお行きあいするのは二度目ですが、もう、一言も聞き逃さず見逃さずの気持ちでAさんに向かって「突進」です。
試合形式の練習をしていると、Aさんの目の前にボールが飛んできました。
しかし、Aさんは反応しません。
周りが「(今のボールはコート内に)入っていましたよー。」と声をかけると、「私95歳で目は見えないし、耳も聞こえないのよ。ボールがね、見えないのよ。」とおっしゃるのです。
そうですよね…そうでしたね…
ラケットを持ってコートの中に立ってはいても、やはり「見えない、聞こえない」なのですね。
見えない聞こえない
確かに!
実は私自身も体育館の中のボールが見づらいのです。
床面には青・白・赤・緑のテープが張られています。
テニスラインは青。
しかし、自分が打ったサーブも相手が打ったサーブも入ったのかどうかが、天井の蛍光灯の光も反射して、外のコートの時以上に見えないのです。

ただ、相手のコートに入ったかどうかはわからなくても、自分に向かって飛んでくるボールは困らない程度に見えています。
そのため上手に打ち返せるかは別として、とにかく安心してボールを追うことができているわけです。
しかし、それもだんだんと困難になっていくのでしょうか。
95歳でテニス教室に通ってくるその外見からは一見想像しづらいのですが、もろもろ過酷な状況を背負いつつもテニスを続けているのでしょう。
その過酷な状況が自分の身にも降りかかりつつあるがゆえに、この人はなんてすごいんだとしみじみ思います。
そのつもりで様子を見ていると、明らかに聞こえていないんだろうなと思えるふしがあります。
コーチから出してもらうボールは、10球打ったら次の人に交代します。
コーチが「はい、交代。」と言ってくれますが、Aさんには聞こえていないようで、まだ次のボールを打とうと構えているのです。
「交代ですよ~。」と少し大きなで声をかけてあげるようにします。
世の中のほぼ全ての場所で行われている「アナウンス」は、95歳の人仕様にはなっていないのだろうなと思わずにはいられません。
スーパーやコンビニのレジで、受診した病院で、場合によっては同じ食卓を囲む家族との会話ですら。
でも、そんな疎外感に負けず、今日も「神」はコートでラケットを振り、後進の者に勇気を与え続けています。
どうする下りゆく中高年
ところで、私は今、目の前で展開される千載一隅ともいえるこの貴重な経験と同時進行で、偶然にも「中高年のありよう」について体系的に学ぶ機会を得ています。
放送大学でズバリ「中高年の心理臨床」という講義の受講真っ最中なのです。
受講の動機は、両親も亡くなり、体力・気力・記憶力も下り坂になってきたけれど、これからいったいどのようなおももちで生きていけばいいのかなと思ったからなのです。
「体重と白髪ばかりがただただ増え続け、年を取り始めたことに気づき始めてしまった私を、だれか助けて~。」という叫びに、この講義は見事に応えてくれました。
中高年も発達し続けている
中高年の実態や課題は、今の自分に直結する内容だけに、『鬼滅の刃』を読むがごとく、全239ページ約1.5センチのテキストを、次へ次へと読みきってしまいました。
テキストの目次は目を引くものばかりです。
- 家族にかかわる心理臨床
- 人生の途中で病・障害をかかえるということ
- 定年退職にかかわる心理臨床
いったいどのページから読もうかというくらい、自分の求める内容にドンピシャです。
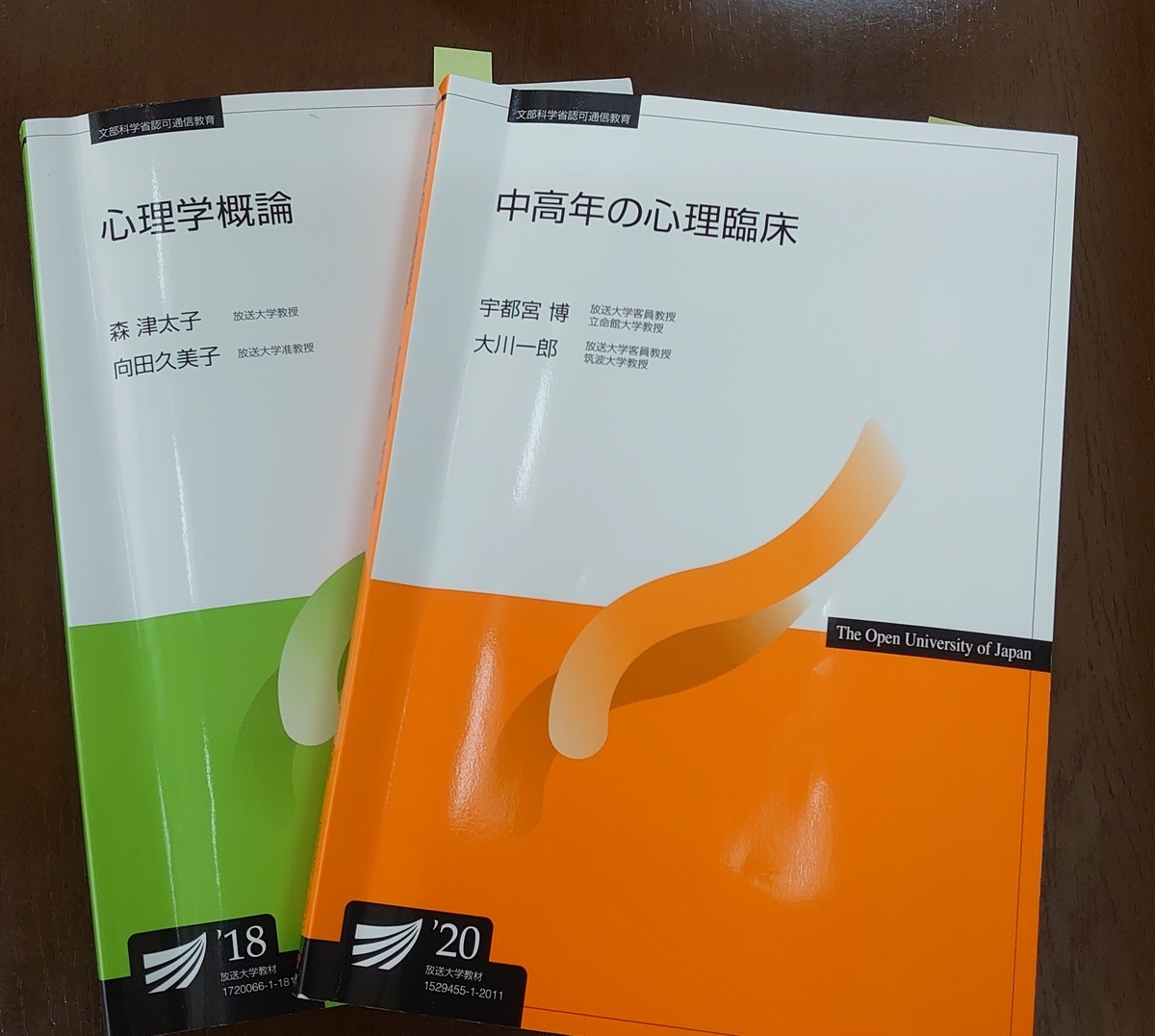
以下、希望の明かりが見えた部分をご紹介します。
「…様々な機能が低下し、資源が乏しくなる高齢者は、多くを求めず、自分の情動を優先し、自分の気持ちがより良い状態になるように様々な選択を行っているとするものである。
このようなメカニズムによって、客観的には喪失を多く経験しているようにみえたとしても、その内面はポジティブな状態にあり、幸福感を感じていることが想定される。」
放送大学教材『中高年の心理臨床’20』 宇都宮 博 大川一郎
更に同時に受講した「心理学概論」の中では、
「…健康な高齢者には、経験を積んだ人ならではの知的能力(結晶性知能や英知)の発達や、肯定的な感情の増加がみられる。
自分の人生を振り返り、意味づけをしながら、老いと向き合い、やがて死を迎える。
こうして一人の人生は終わるが、その軌跡は次の世代に引き継がれていく。」
放送大学教材 『心理学概論’18』森 津太子 向田久美子
救いが見つかってきました…!
生きていく上での支えや備えとして、このようなとらえ方えを、知らないより知っていたほうがいいような気がするのですが。
皆さんは、どう思われますか。